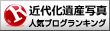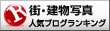【名称】不明
【所在地】南房総市和田町中三原
【竣工】不明(明治初期?)
【延長】約15m(目測)
【幅員】約2m(目測)
【高さ】約2m(目測)
2017年7月16日訪問
![]()
南房総市和田町中三原(なかみはら)、千葉県道296号和田丸山館山線(わだまるやまたてやません)にて。今いるのはココ(←クリック)。昨日紹介した寺谷トンネルの東側である。
実は先日、拙ブログに南房総在住の雲助2号さまという方から、重大情報がもたらされたのだ。せっかくの素晴らしい情報なので、勝手ながら引用させていただくことに。
寺谷トンネルですが、旧隧道が存在します。
アプローチ方法は、トンネル東側坑門から150m和田寄りの南側(海側)の落石注意の標識の所から、法面の吹き付けと一体となった路盤があります。
0.5車線の道で坑門上を横断すると、縦横2m、延長15mほどの四角い素彫隧道があります。
東側アプローチが直角なので、軽自動車でも通行出来なかったと思われます。
地元の知り合いに聞くと、現寺谷トンネルは、素彫隧道を拡幅したとのことなので、現役期間は短かったと思われます。
な、な、なんだって、旧隧道!?∑(゚Д゚) こいつは、すぐにでも調査しなけりゃ!!
![]()
(この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)により作成したものです。)
実は、今さら言うのもなんなのだが、この隧道の旧隧道の可能性は、以前からおいらも考えていた。これは明治末に発行された地形図と現在の地理院地図。両者を見比べると、西側の道の線形が微妙に違う。とはいえ、どちらに描かれた隧道も尾根の真下を水平に通っているので、誤差の可能性の方が高そうなので、機会があったら調査すればいいや、ぐらいに思っていた。
ところが、そんなところに思わぬ情報。図らずもおいらの見立てが正しかったのか!? と思ったのだが、それ自体はやはりただの妄想だったようだ(^-^; というのも、雲助2号さんの説明による東側の接道の様子と明治末の地形図の様子が違うからだ。
![]()
(この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)により作成したものです。)
そこで、今度は迅速測図を見てみたのだが、仰天した。現トンネルとほぼ同じ位置に、短い隧道のマークがあるではないか!そして、東側の接道は大きく南側から回り込んでいる。雲助2号さんの説明の通りの線形ではないか!∑(゚Д゚) つまり、これが旧隧道、そして明治末の地形図にある隧道は改修される前の(現)寺谷トンネルであると考えるべきだろう。
迅速測図に載っているということは、この隧道は遅くとも明治十年代半ばには完成していたということになる。ということは、この隧道、500本以上あると言われる房総の隧道の中でも最も古いもののひとつだろう。そして、明治末には今の隧道に切り替わっているので、廃止されて既に100年程度経過しているということか?い、い、一体、今はどういう姿になっているのだろう、、、すごいことになってきたぞ(゚д゚; )ゴクリ
![]()
とまぁ、そんな経緯があってここにやってきたのだ。
なお、途中、まきき氏の自宅の近くを通るので、念のために声を掛けてみると、、、
「はぁ!? こらっ、おっさん! ワシは毎日仕事で忙しくてもう1ヶ月も穴にご無沙汰なんじゃ! 欲求不満の溜まりまくりなんじゃ! え、どうしても一緒に来て欲しいって? 仕方ないなぁ、そんなに頼まれたら付き合ってやってもいいで! ほら、はよワシの車に乗れや、行くで!!」的なお返事(脳内翻訳済)が。
まきき氏もやはり、雲助2号さんのコメントを見てウズウズしていたらしい(^-^;
![]()
さて、情報によれば、「和田寄りの南側(海側)の落石注意の標識の所から、法面の吹き付けと一体となった路盤が」あるとのこと。うん、ここで間違いない。ってか、刈り払いされてるし(゚д゚)ハッ!!
![]()
まるで、我々の訪問を予期して準備されていたかのような好展開。「えー、なになに、もしかして、『アイツ、そろそろ見に来る頃かな?しょーがねー、いっちょ刈り払いでもしといてやっか』って事で準備しておいてくれたんじゃね?いやー、ありがとうございます、ゴチになります!」なんて会話をしながら、まきき氏と歩みを進める。まきき氏と一緒に出かけると、妄想モードに入ることが多いののはどういうことだろう?(^-^;
![]()
登り始めた地点は、ホントに路盤なのか半信半疑な雰囲気だったのだが、この辺りまで来ると完全に道の様子に。
![]()
道はそのまま山林の中に伸びている。
![]()
杭だ!(゚д゚)ハッ!!
![]()
山林に入るとビックリ。見事な道があるではないか。
![]()
植林地によくある作業道よりも広めの道。素晴らしい古道だ(*´д`*)ハァハァ
![]()
稜線が見えてきた。
![]()
崩落したのだろうか、ここが道中で一番道幅が狭くなっていた場所。とはいえ、特に危うさを感じることはなかった。
![]()
そして、最後の登り坂の先に見えてきた!(゚д゚)ハッ!!
![]()
おおっ!!!あったぞ!思わず声を上げてしまった。
![]()
東側坑口。
廃止されてから約一世紀経っているとは思えない程の良好な隧道。実のところ、この隧道の話を聞いて、想像したのは、藪をかき分けた奥にある閉塞しかかった小さな穴ぼこの姿だった。あまりにもアブナイ雰囲気だったら、まきき氏だけを蹴飛ばして放り込めばいいや、と思っていたのだが、予想は良い意味で裏切られた。こいつはスゲー。
![]()
それにしても土被り少なっ。ここまで頑張って山を登ってきたのだから、切り通しでも良さそうなのに、、、 隧道趣味業界でよく言われる「房州人の掘らなくてもいい所でもつい掘っちゃう癖」の萌芽がここにも見られるのか? と冗談めかしてみたが、この隧道の上に、先ほどの迅速測図にも描かれている南北に走る稜線上の道が残っている。その道を残すために、あえてここは隧道にしたのかもしれない。
![]()
東側坑口、向かって右側にある凹み。お地蔵さんか馬頭観音(南房総だから牛頭観音か?)、もしくは石碑などが置かれていたスペースだろうか。
![]()
左側にもやはり何かを安置していたであろうと思われる凹みが。この隧道の前後にある隧道、切り通し、隧道開削跡の切り通しには地蔵や牛頭観音、馬頭観音の碑が置かれていた。ここにも同じような風習があったのではないだろうか。ただ、(現)寺谷トンネルには石碑類が一切残っていないのが気になるが、、、
![]()
東側坑口から内部を望む。ほぼ四角の断面。房総の古い素掘隧道は五角形の観音掘が定番なので、少し意外な感じがした。ここでまた妄想モードに突入、、、
百数十年前の会話
「おい、マキ作、あそこの峠に穴掘るっぺか?」
「おっ、パパ兵衛、隧道ってやつだっぺ。掘るっぺ」
「ところで、隧道って掘ったことあるっぺか?」
「いや、ねえっぺ。だが、二五穴のでっけーもんじゃねえっぺか?」
「そだな、じゃあ二五穴の要領でいくっぺか」
という案配で断面が四角になったのではと、、、 えーと、これも、あくまで妄想だ(^-^;
![]()
内部から見た東側坑口。
![]()
この凹みは何のために?
![]()
ここなど、路傍にある牛頭観音がぴったり納まりそうだ。
![]()
穴の中にいる小さな黒いモノは、、、、(^-^;
![]()
西側へ。
![]()
西側の道は若干荒れ気味。
![]()
振り返って、西側坑口から内部を望む。
![]()
西側坑口。
![]()
こちら側も、崩落してきた土砂が積もっているものの、往時の姿をよく残していると思われる。
![]()
この隧道、幹線道路としては相当昔にお役ご免になったが、その後もそれなりに訪れる人がいたようだ。この後、たまたま近くの年配の方に話を伺ったら、その方も幼い頃にここを遊び場にしていたとのこと。地元の方々にはお馴染みの場所のようだ。
![]()
さて、西側の道は勾配が急。早い時期に廃止になったのは、こちら側の道のせいもあったかもしれない。
![]()
そして、藪で行き止まりに。無理すれば進めないこともないが、そこまでする気にもなれずに、ここで引き返すことに。写真では解りにくいが、左上に県道が見える。隧道は現トンネルのほぼ真上に位置しているが、西側の道は若干南西方向に向かっているようだ。
![]()
どや、わしの言った通りだろ!と得意げなまきき氏。しまった、出たがり屋さんのまきき氏の写真、あまり撮っていなかったよ。ごめんね。
そして、雲助2号さん、貴重な情報、ありがとうございました。
※ ※ ※
おまけ動画。
![にほんブログ村 その他生活ブログ 道・道路へ]()
にほんブログ村
![]()
古道・廃道 ブログランキングへ
![]()
![]()
第七十一番 弥谷寺![]()