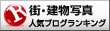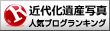【名称】小原澤橋(こはらさわばし)
【所在地】夷隅郡大多喜町横山
【竣工】1960(S35)年3月
【橋長】約5m(目測)
【幅員】約3m(目測)
2017年3月12日訪問
大多喜町泉水(せんずい)、千葉県道172号大多喜里見線(おおたきさとみせん)にて。今いるのはココ(←クリック)。
法面がコンクリ施工されていないので地層が剥き出し。県道とはいえ、交通量も少ないのであまり熱心に整備されていないのか?ただ、この道は、明治の初めの地図にもしっかりと記されている道。そして、この近くにあった泉水隧道(開削済)は明治10年竣工で、もし現存していたら県内でも有数の古隧道だったはずのものだった。
少し進んでマクレガーCCの入口を過ぎた辺りだっただろうか。歩道に生えていた枯れ草を見て思い出した。これ、「ヤ●キ●の金髪頭みたいだぞ」と(^-^;
すると、●ン●ーの生首が並んでいるように見えてきた…。とっとと行こう(^-^;
さらに進んで、上原と横山の境界。今いるのはココ(←クリック)。あれっ、横山って国道297号と県道27号の交差点じゃないっけ?と思ったら、ここもそれと同じ横山だった。意外と広いんだな…
本題から逸れるのだが、googleマップを見て面白いことに気付いた。
これを見ると、横山の東の地域にボツボツと小さな穴が開いている。なんじゃこりゃ?まさか飛び地?
飛び地は大多喜町猿稲のものだった。東金市と八街市の境界付近にもゴチャゴチャと小さな飛び地があるが、ここの飛び地はもっと小さい。なにしろ、千葉トヨタの建物の半分とかデイリーヤマザキの建物部分のみだったりとかなのだ(^-^;
ともかく、この路地を入る。この先は完全に横山。
目印は法面の上にちょこんと乗った石碑だ。
この道は最終的に伊藤集落で行き止まりとなるのだが、目的地はその手前にある。
こういう狭い道は対向車が気になって落ち着かないので、チャリが快適だ。
伊藤浄水場。
小さな橋が見えてきた。
南側より。
南側左の親柱。「小原澤橋」
南側右の親柱。「昭和三十五年三月竣功」
西側より。
橋の上から西の上流方面を望む。
東の下流方面。この川だが、「小原澤橋」というのだから、小原沢じゃないかとおもったのだが、このまま直接、平蔵川(養老川水系)に繋がっているので平蔵川ということになるのだろうが、上流部分は小原沢なのかもしれない。ま、まぁ、正直よくわからない(^-^;
なお、平蔵川だが、『角川日本地名大辞典12千葉県』によれば、
「上流には河川争奪の結果、夷隅川によって流路が切り取られたことを示す空谷(元の谷の横断面が新しい分水界の稜線として残ったもの)がみられる」(同書 p.753)
とのこと。
えーっと、微妙に意味がよくわからないのだが、要は夷隅川に水をぶんどられて、旧流路の名残が残っているということか?面白そうなのだが、どこのことなのかさっぱりわからない(^-^; 伊藤大山の南東側に夷隅川の支流があるので、それが平蔵川の上流から水をぶんどった流れなのかもしれない。まったくの憶測だが。
北側より。
北側左の親柱。「こはらさわばし」
北側右の親柱。「昭和三十五年三月竣功」
東側より。
北側の道の先にちょっと面白いものが…
ロープが張ってあったので、直接中には入らなかったのだが、対岸から見ると穴が、、、物置なのかな?
ラブライブ!サンシャイン!! 小原鞠莉エモーショナル Tシャツ ブラック Lサイズ