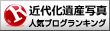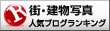【名称】不明
【所在地】君津市笹
【竣工】不明
【延長】約3m(目測)
【幅員】約4m(目測)
【高さ】約4m(目測)
2012年1月29日訪問
もう5年近くも前のこと。片倉ダム近くの駐車場でお馴染みの面々(doodoongoo氏、まきき氏)と待ち合わせ。だが、この日はもう一人のスペシャルゲストがいた。その人は、この日のためにわざわざ関西からやってきたのだ(嘘)
「はじめまして、クイック・ニック(←当時)です ( ̄- ̄)ズーン」
「は、は、はいぃぃぃ、ぱ、ぱ、パパゲーノと申します。よろしくお願いします (_ _(--;(_ _(--; ペコペコ」
さて、まきき氏に引率されてやってきた最初の目的地。君津市笹の千葉県道24号千葉鴨川線(ちばかもがわせん)にて。今いるのはココ(←クリック)で北を向いている。
この先が、現在の地図にも残る南の細い道から続く旧道らしいとのこと。
(この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)により作成したものです。)
ここで今昔マップで新旧地形図の比較してみよう。左が明治39年に発行された地形図。右は現在の地理院地図である。大きくカーブを描く現道に対し、旧道はその部分をショートカットしている。地図で見る限りでは、旧道の方が線形がスマートだが、まぁ、それは地形的な問題があるからだ(^-^;
そして、赤丸の中にしっかりと隧道の記号が描かれている。なお、現道をショートカットする区間は昭和22年発行の地形図ではすでにキレイさっぱり消えている。
では旧道に突入。
旧道は現道より1メートル程高い位置にある。
振り返り。
しかし、少し先で道は大きな下り坂に。これが現道に切り替えられた大きな理由のひとつなのだろう。
坂を下りきった先で道はわからなくなってしまった。耕作地に転用されたようだ。
とりあえず、進めるところを適当に隧道擬定地に向かって進む。すると、先頭を歩くdoodoongoo氏の声が。
「あったよー」(゚д゚)ハッ!!
声の聞こえる方向に向かうとそれがあった。
真四角の断面を持つ素掘隧道。南側より。
だが、隧道内に道はなく、水路が通っていた。
北側より。う~ん、水路隧道になっているけど?(^-^;
ひょっとしたら地図の隧道とは別のものかもしれない、ということで、隧道の上に登ってとりあえず東側に向かう。上を歩いたのにはあまり意味はない(^-^;
数百メートル進むも、別の隧道は現れない。ということで、北側の川(小櫃川水系・清水川)に降りて、先ほどの隧道まで戻ることに。
つららがびっしり。
その一本を掴んだクイック・ニック(現・クイック)氏。この後、凄惨な事件が発生、、、してはいない(^-^;
再び隧道の北側に戻ってきた。
川の中に杭のようなものが立っていた。
当時ものとも思えないが、橋の跡だったのかもしれない。
さて、今度は上流方面へ。
さすがに1月に川の中を歩くのは冷たい(^-^;
今度は小さな穴が登場 ∑(゚Д゚)
穴の手前に思いがけないものがあった。
レール(を加工した柵?) ∑(゚Д゚)
今、某サイトで盛り上がっている房総の林鉄跡はこの近く。このレールもそれに関係あるのかもしれない。この時も、皆でアヤシイと話したのだが、やっぱり林鉄があったのね。
この穴、どうしてくれよう、、、
と思っていたら、クイック・ニック氏(当時)がアタック開始 ∑(゚Д゚)
負けず嫌いのまきき氏も続く(^-^;
さらにしばらく歩くと現道の片倉橋が見えてきた。
ここで現道に復帰。
ということで、現在では水路隧道となっているものが旧道の隧道であることが確定。
TANG タン メンズ 片倉小十郎 戦国武将家紋シリーズ ハーフパンツ スポーツ ショートパンツ 記念 ギフト Black Medium