【名称】不明(木橋)
【所在地】夷隅郡大多喜町大多喜
【竣工】不明
【幅員】約1m(目測)
2013年6月23日訪問
現在地はココ(←クリック) 千葉県道172号大多喜里見線(おおたきさとみせん)から小さな分岐道がある。
少し奥に入ると林道の標識が。ここから林道泉水西部田線になる。
入り口のいかにもタイトな雰囲気がちょっと不安…
が、いざ進んでみると、広い幅員にきれいな舗装。ヨカッター
道はほぼずっと下り。快調にチャリで進む。
ここで、右に未舗装の歩道があった。なぜか入り口の写真は撮り忘れ(^-^;
この辺りはたぶんヤマビルは出ないはず。
この下には? さっきの看板には砂防ダムがあると書いてあったけど…
おおっ、立派な木橋が。
右にも。
全体はこんな感じ。写真はパノラマ合成。
まずは右に行ってみよう。
一本渡るともう一本。
ここで道は終了。
その先を見ると砂防ダムが。おそらく第二号砂防ダム。
※ ※ ※
次は左に行ってみよう。
おっ、砂防ダムが見えてきたぞ。
橋を渡りきったところ(南端)には水路隧道を塞いだらしき跡が。
振り返り。南側から見ている事にある。
※ ※ ※
【名称】第一号砂防ダム
【所在地】夷隅郡大多喜町大多喜
【竣工】1977(S55)年12月
【堤高】10.7m
【堤長】27.9m
2013年6月23日訪問
これが多分さっきの看板に書いてあった砂防ダムの事だろう。
正面(南側)より。
銘板のアップ。
※ ※ ※
【名称】泉水西部田橋
【所在地】夷隅郡大多喜町大多喜
【竣工】1987(S62)年頃
【橋長】10.74m
【幅員】約4m(目測)
2013年6月23日訪問
砂防ダムの先で再び林道に復帰。
林道に出て北方向を振り返る。
橋を南側より。
橋の上から西の上流方面(砂防ダム方面)を望む。
東の下流方面。
北側より。
こちら側には立派な銘板もある。
「昭和62年度/林道開設事業/夷隅郡大多喜町大多喜地内/橋名 泉水西部田橋L=10.74M/施工主体 千葉県南部林業事務所/施工者 小倉建設(株)」
地理 ブログランキングへ
にほんブログ村
泉水西部田線の諸々
大船谷隧道
【名称】大船谷隧道(おおふなやずいどう)
【所在地】いすみ市大原
【竣工】不明
【延長】約50m(目測)
【幅員】約5m(目測)
【高さ】約4m(目測)
2014年7月27日訪問
いすみ市大原、場所はココ(←クリック) 6時の方向を向いている。
この先の道は、今昔マップの1972~1982年の地形図には載っていないなので、比較的最近開通したのだろう。
左の分岐の先に古めかしい隧道が見える。そう、こちらの道は古くからあるようだ。
知らずに勢いで入って来ちゃう人が多いんだろうなぁ(^-^;
隧道の手前は深い掘割になっている。
北側坑口。
北側の扁額。葉に隠されて何が書いてあるのか解らない(^-^;
北側坑口から内部を望む。
内部から見た北側坑口。
延長は50メートル程だろうか。内部は完全にコンクリートで巻きたててある。
南に抜けると、右手に緩やかな登坂のようなものが。まさかの旧道?
少し先に進んだところ。ってか、旧道ってのはちょっと考えすぎだろうねぇ(^-^;
さて、坑口の観察に戻ろう。
南側坑口。
坑口の手前に、何かを備える穴が。祠や仏像などは入っていない。
南側の扁額。「おおふなやずいどう」
南側坑口から内部を望む。
内部から見た南側坑口。
もう一枚、南側より。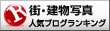
街・建物写真 ブログランキングへ
にほんブログ村
E233系 京浜東北線 快速 (大宮~大船) [DVD]
山中橋
【名称】山中橋(やまなかばし)
【所在地】山武郡芝山町山中
【竣工】1964(S39)年3月
【延長】約10m(目測)
【幅員】約3m(目測)
2014年8月24日訪問
山武郡芝山町、成田空港から飛び立った飛行機が見える。千葉にあるのに東京●ィ●ニーランドとか東京●イ●村なんてい言うが、成田空港は10年前に正式名称を新東京国際空港から成田国際空港に変更した。
ということで、今回の目的地は写真中央、だいぶ見づらいが高谷川に架かる橋だ。
北側の道から行く。
北側より。
北側右の親柱。
「やまなかばし」
正直に言うと、これを見た時は読み方がわからなかった(^-^; 香取~山武のエリアは変体仮名を使っていることが多いなぁ。
北側左の親柱。「昭和丗九年三月竣工」
橋の上から東の下流方面を望む。
西の上流方面。
南側より。
南側右の親柱。「山中橋」
南側左の親柱。「昭和丗九年三月竣工」
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた
地理 ブログランキングへ
にほんブログ村
(仮称)杉戸隧道
【名称】不明
【所在地】勝浦市松野
【竣工】不明
【延長】約100m(地図読み)
【幅員】約3m(目測)
【高さ】約3m(目測)
2014年12月8日訪問
そうだ、勝浦に行こう!日曜日の朝、思い立って勝浦の旅館・松の家さんに行ってきた。いつものように腹一杯食べて、寝て、夜中に起きて酒を呑みながら読書して… と自堕落に過ごした翌朝。
飲み過ぎでちょっとくたびれている割には、朝からご飯も4杯。ここに来るといつもこうなるんだよなぁ(^-^;
さて、松の家を出て20分後。ココ(←クリック)に来た。
溜め池の築堤。
大谷溜池というらしい。
白い枠は取水口みたいなやつ?
このフェンスは立ち入りを制限するものではなく、イノシシやシカのような害獣をブロックするためのもの。開けたらちゃんと閉めて鍵をかけて進む。
ここから隧道まで、順調なら400メートルほど。まきき氏は苦労したようだが、今日はどうだろう?
今のところ道は順調。
ネット上では杉戸第3支線とするサイトもある。
溜め池を東西に分ける築堤。東西の溜め池は暗渠でつながっているのかな?
築堤の東側。
西側(パノラマ合成)
築堤の先で急に道が荒れ始める。
いやっ、まだまだいける… はず!?
あぁ… もう無理 …(;´Д`)ウウッ…
大したことなさそうに見えるかもしれないが、このすぐ左は溜め池。うっかり足を滑らせて落っこちたりしたらシャレにならない(^-^; ということで、撤退。
しかし、こんな事もあろうかと、次の作戦も用意してあるのだ。
※ ※ ※
15分後…
場所はココ(←クリック)
この先、ゲートで封鎖されているという話だが、行けるところまで来るまで行ってみようという作戦だ。
と こ ろ が ・・・
「なんじゃこりゃ~~~」Σ(゚д゚lll)ガーン
思わずステアリングを握ったまま叫んでしまった。鬼バックしろって?無事に戻れるのか?「オワタ」と思った瞬間。
場所はココ(←クリック)なので、行ってみようと思っている方はご注意を。
しかし運良く、少しだけ戻った所に転回可能なスペースがあった。とりあえず、車の向きを変えて停車。隧道までは結構距離がありそうなので、チャリで行くことにした。
こうして停めておけば、おいらのように、ここまでに入り込んでガーンになった人も戻ることができるだろう。写真手前が崩落側。
崩落の向こうは平穏な様子。
ここがバッサリと崩れてきたのね(^-^;
この先、民間の建物があったが、この状態でどうしているのだろう(^-^;
井堰上ダム。堤高18メートルの灌漑用アースダム。
ダムを過ぎてしばらく進むと、いよいよゲートが現れる。この先は一般車進入禁止(南に進入可能なゲートがあるようだが)。なお、肝心のゲートの写真は撮り忘れてしまった。帰りに撮ればいいや、と思ったら帰りにも忘れてしまったという… (^-^;
第1支線との分岐手前にるコンクリート橋。
銘板は4枚とも残っているのだが、読み取れず(^-^;
橋のすぐ先でコンクリ舗装が始まった。こりゃ楽ちんだ。
上り坂で汗をかき始めた頃、ようやく目的の分岐までたどり着いた。場所はココ(←クリック)
おかしいなぁ、まきき氏はじめ、ネットでみたレポートによれば、林道の本線から隧道が見えるってことだったのに(^-^;
倒木やら草が… ちなみに手前の、たぶんコイツだと思うのだが、かき分けて進んだら、ズボンと上着にたっぷりと少しヌラヌラした種?をくっつけてくれた。あとで20分近く服を叩くハメになった。たしか、前にも2~3回やられたことがあるんだよなぁ。とりあえず種を取り除いちゃえば、ヌラヌラ成分は洗濯すれば簡単に洗い流せるけど。
ここは沢ですか?(^-^;
そして、前方からはポチャーン、ポチャーンと残響を伴った音が聞こえてくる。イヤーな予感(^-^;
この向こうにあるな…
がれきの上に登ると、見えた!」
西側坑口。
林道によくあるタイプの正方形断面の隧道だ。
隧道内部は乾燥しているようだが、手前が水没。さっきから聞こえるポチャーンは坑口の上から手前の池に落ちる水の音だった。なんとか突破できるルートはないかなぁ…
無理・・・
ここで、地下壕の大家K氏の奥義・水陸両用ができればいいのだが、おいらはそんなに根性座っていないので…(;´Д`)ウウッ…
隧道の中は真っ暗。閉塞?それとも崩れているだけで貫通はしている?
LEDライトの明かりを目一杯絞って照らしてみたが、よくわからず。。。
古道・廃道 ブログランキングへ
にほんブログ村
ゼンリン地図ソフト デジタウン 杉戸町 (埼玉県) 発行年月201410 114640Z0F
水沢橋
【名称】水沢橋(みずさわはし)
【所在地】南アルプス市芦安芦倉
【竣工】1962(S37)10月
【橋長】約10m(目測)
【幅員】約4m(目測)
2014年10月26日訪問
山梨県道37号南アルプス公園線、そのマイカー規制区間をひとりトボトボと奈良田方面に歩いている。
あれ、木にリボンが結びつけてあるぞ。
下を見ると虎ロープが。これはちょっと遠慮しときます(^-^;
ということで、前進。
小さな橋が見えてきた。
北側より。残念ながら無名橋。
橋の上から西の山側を見たところ。
枯れ沢のようだが、雨のあとは滝が見られるのかな?
※ ※ ※
続けてすぐに次の橋に。こちらは親柱もしっかりあるぞ。
水沢橋というらしい。
北側左の親柱。「水沢橋」
実は最初に親柱の銘板を見て、「あぁ、木沢橋かぁ」と思った(^-^;
でも、次にこっちを見て勘違いに気づいた。
北側右の親柱。「みずさわはし」
そうそう、左側の親柱にはもう一枚銘板があった。「昭和三十七年十月完成」
橋の上から西の山側を。こりゃきれいな滝だ。
と、嬉しくなったのだが、実はこの後、この景色はなにも特別ではないということに気づくという(^-^; 次にここを歩く時は、もっとひとつひとつ違いを確かめながら… いや、そんなことしていると時間がなくなるかも(笑) いや、写真を撮りながらチンタラ歩いていたら、予定の倍の時間がかかってしまったので(^-^;
東の野呂川(早川)方面。
下を見ると野呂川に流れ出す流れが見える。
南側より。
南側左の親柱。「水沢橋」
この親柱にも第二の銘板が。「昭和三十七年十月竣功」 たしか北側のものは「完成」だったのに。こういう表記の揺れ、突っ込むつもりは全くないのだが、気づいてしまうと、どいういう経緯があったのか、勝手にいろいろと変な想像してニヤニヤしてしまう。そうだ、また久しぶりに現場監督Dと生真面目な部下Mの物語でも書いてみようか(・∀・)ニヤニヤ
南側右の親柱。「みずさわはし」
もう一枚南側より。
橋を過ぎて、再び奈良田方面に歩みを進める。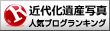
近代化遺産 ブログランキングへ
にほんブログ村
AKI MIZUSAWA―PHOTOGRAPHY KISHIN SHINOYAMA 1975‐1995
(仮称)九十九谷隧道
【名称】不明
【所在地】君津市平田
【竣工】不明
【延長】約50m(目測)
【幅員】約3m(目測)
【高さ】約3m(目測)
2013年9月22日訪問
君津市平田にあるジャパンPGAゴルフクラブ。この入り口のすぐ手前に右に分岐する謎の道がある。
ネットの地図では、この先でゴルフ場内にあるグリーンの脇を通る道(航空写真に写っている)につながっているように描かれているが、それは間違い。実際は別の道だ。
数年前のある日、国道465号を走っていたまきき氏は車の不調を感じて、整備できる場所を探してここに入り込んだそうだ
(´-`).。oO(なぜにこんな所を選ぶ?w)
で、舗装の切れるどん詰まりまでやってきたそうだ。
(´-`).。oO(行き止まりと解っている道でもどん詰まりまで行くのがまきき氏流)
ところが、まきき氏、肝心の整備より道の先が気になってしまったらしい
(´-`).。oO(車の整備はどうした)
で、途切れた舗装の先に潜り込んでみたそうだ。
(´-`).。oO(確かにここまで来るとなにかありそうな気がするかも)
左はこんな様子。この向こうはたぶん10番ホール。
そして・・・
(´-`).。oO(ビックリの展開があるんだな)
右を見ると、素掘り隧道が!!!
(´-`).。oO(まきき氏の隧道アンテナ全力稼働)
隧道の神からの思わぬ贈り物。感激したまきき氏は思わずその場に跪き、隧道の神に感謝の祈りをささげたという。
(´-`).。oO(これだけはおいらの作り話。いや、でも実際そうだったかも)
まきき氏のレポはこちら↓
J-PGA隧道(仮称) - 2008年 2月 22日(金)
それにしても「J-PGA隧道」ってのはちょっとかわいそうでしょーw ってことで、他の仮称を考えておくとまきき氏には伝えておいたのだが、なかなかいい呼び方が思い当たらず、近くの地名を頂いてしまった。九十九谷というのは隧道の北西方面一帯の呼び名のようで、鹿野山の展望台にもその名が使われている。なお、読み方は「クジュウクタニ」。「ツクモタニ」とか「ツヅラヤツ」って読んでしまいそう。ちなみに、近くにある九十九トンネルは「平成16年度道路施設現況調査」によれば「ツクモトンネル」と呼ぶようだ。
地名関係でもうひとつ付け加えると、ここの住所の君津市平田だが、「ひらった」と読む。そして近所の平田トンネルは「平成16年度道路施設現況調査」によれば「ヒラタトンネル」
んん~ (^-^;
もっとも、「平成16年度道路施設現況調査」の隧道名、時々アヤシイと思えるものもあるのだけど…
南側坑口。
日暮れ近くで隧道の手前は薄暗かった。崩落のため、坑口の手前には50センチほどの高さに土が積み上がっていた。
南側坑口から内部を望む。
間違って隧道の中に生えて来ちゃった竹。残念ながら力尽きている(^-^;
内部は崩落もなく綺麗。道床はさらさらとした砂の感触。
内部から見た南側坑口。
おいらの侵入に驚いたのか、コウモリが2~3羽、羽ばたき始めた。驚かせてごめんよ。でも、おいらも驚いたんだ(^-^;
この日は乾燥していたが、雨が続くと水没することもあるようだ。壁面の跡を見ると、多いときには15~20センチぐらい水が溜まるのかもしれない。
内部から見た北側坑口。
こちらは崩落も少なく状態良好の予感。
北側坑口。
北側坑口から内部を望む。
(確か)右側の内壁にあった穴。時々こういう穴を見かけるが、蝋燭でも置かれていたのだろうか?
隧道北の道は完全廃道状態。
少し古めの地図を見ると、このまま北の道につながる道筋が描かれている(隧道の記号はなし)。北西に「植畑村他四村入会」という地名があるので、入会地へのアクセスルートになっていたのだろう。
たぶん100~200メートルぐらい藪こぎすれば、北側の舗装路に出られると思うのだが、日暮れも近いし、汚れてもいい準備をしてこなかったので、ここで引き返した。
※ ※ ※
おまけ
国道465号からゴルフ場方面に向かう交差点近くにある穴。
防空壕にしては大きすぎるようだし、奥行きもなさそうだし…
古道・廃道 ブログランキングへ
にほんブログ村
露伴九十九章
いしばし橋
【名称】いしばし橋
【所在地】成田市郷部
【竣工】1982(S57)年3月
【橋長】約30m(目測)
【幅員】約4m(目測)
2014年6月29日訪問
利根川の支流・根木名川のさらに支流・小橋川、その指定区間のもっとも上流川に架かる橋。なんだか長い説明になったなぁ(^-^;
東側より。
南側より。
まぁ、普通の橋だ(^-^;
南側左の銘板。「いしばし橋」 右には銘板はなし。
この日は初夏だった。このときはいい天気だったのだが、数時間後、にわか雨に降られて、挙げ句の果てにはチャリをパクられるハメに…
橋の上から東の上流方面を望む。
右手に見える水門。
水門の銘板。
西の下流方面。
北側より。
北側右の銘板。「竣工昭和57年3月」 左の銘板はなし。
地理 ブログランキングへ
にほんブログ村
石橋杏奈 写真集 『 LEAP 』
長者橋
【名称】長者橋0(ちょうじゃはし)
【所在地】茂原市早野
【竣工】1974(S49)年3月
【延長】約30m(目測)
【幅員】約1.5m(目測)
2013年7月28日訪問
一宮川の支流、阿久川の一番下流に架かる橋。東側より。
北側より。
北側右の親柱。「長者橋」
北側左の親柱。「阿久川」
橋の上から東の上流方面を望む。
西の下流方面。このすぐ先で一宮川に合流している。
南側より。
袂から。
南側右の親柱。「ちようじやはし」
南側左の親柱。「昭和49年3月竣工」
※ ※ ※
【名称】不明
【所在地】茂原市早野
【竣工】不明
【延長】約30m(目測)
【幅員】約1.5m(目測)
2013年7月28日訪問
一宮川に出て川沿いに上流方面に。今度はどんな橋だろう。
東側より。こちらは残念ながら無名橋。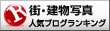
街・建物写真 ブログランキングへ
にほんブログ村
あなたも株長者になれる39の秘訣
小山隧道
【名称】小山隧道(こやまずいどう)
【所在地】いすみ市大原
【竣工】1972(S47)年(「平成16年度道路施設現況調査」より)
【延長】60m(同上)
【幅員】5.0m(同上)
【高さ】3.2m(同上)
2014年7月27日訪問
いすみ市大原の市道にて。現在地はココ(←クリック) 正面は地図上で10時の方角。
隧道発見!(^-^;
ネタにしたコルゲート管の先を進むとカーブの先に隧道が現れる。
南側より。
南側坑口。
この隧道も近所のいくつかの隧道の例に漏れず、「平成16年度道路施設現況調査」によれば建設年次は昭和47年ということになっているが、戦前の地形図にも描かれている。周囲に旧道の痕跡はないし、古地形図に描かれている道路の線形も今と同じようなので、拡幅されているのだろう。
隧道手前のスペース。
隧道前後の路肩に広いスペースがあるのはよく見かけるが、ここはなんというか、何か曰くありげというか… この時も、なんとなく気になって写真を撮ったのだが、写真を見返していて、ひょっとしたら山への作業道の入り口なのかも?と思ったり。
ところで、戦前の地形図には隧道の上に点線道が描かれている。少し不思議なのだが、現在、この付近から南の岩船方面に行くのには一旦国道128号まで出る必要がある。あまり地域間の交流がないのだろうか?
南側の扁額。「こやまずいどう」
南側坑口から内部を望む。内部はすぐにモルタル吹きつけになっている。
内部から見た南側坑口。
隧道の延長は60メートル。南側は2メートル程で巻き立てが終了してしまったが、北側は半分位は巻き立てられている。
北側坑口。
北側の扁額。「小山隧道」
北側坑口から内部を望む。
内部から見た北側坑口。
北側より。
地理 ブログランキングへ
にほんブログ村
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番
御蔵芝橋
【名称】御蔵芝橋(みくらしばはし)
【所在地】茂原市御蔵芝
【竣工】1975(S50)年3月
【橋長】約30m(目測)
【幅員】約8m(目測)
2014年6月1日訪問
北日当橋を後にして、南白亀川の左岸を上流方面に。
清水排水機場。場所はココ(←クリック)
さらにダートを進む。
次の橋が見えてきた。
東側より。
東側右の親柱。「昭和五十年三月竣功」
東側左の親橋。「みくらはし」
橋の上から南の下流方面を望む。
北の上流方面。
西側より。
西側左の親柱。「御蔵芝橋」
西側右の親柱。「南白亀川」
東側の袂から。入り口は少し荒れているが、その先は普通の砂利だったので、こちら岸の道を選んだ。
北側より。
はじめまして三倉茉奈です。はじめまして三倉佳奈です。
地理 ブログランキングへ
にほんブログ村
水沢第一洞門、第二洞門
【名称】水沢第一洞門、水沢第二洞門
【所在地】南アルプス市芦安芦倉
【竣工】不明
【延長】約30m(目測)
【幅員】約4m(目測)
【高さ】約4m(目測)
2014年10月26日訪問
山梨県道37号南アルプス公園線。水沢橋を過ぎて南(奈良田方面)に歩いている。
橋、隧道に続いて今回は洞門の登場だ。
結構歩いたはずなのに、残りはまだ9割近く。あれ、大丈夫か?ちょっと心配になってきた(^-^;
考えていても仕方ないので進むのみ(^-^;
最初の洞門。西側より。
名前は「水沢第一洞門」
すぐに次の洞門が見える。
東側より。
※ ※ ※
【名称】水沢第一洞門、水沢第二洞門
【所在地】南アルプス市芦安芦倉
【竣工】不明
【延長】約30m(目測)
【幅員】約4m(目測)
【高さ】約4m(目測)
2014年10月26日訪問
続いて次の洞門に。
名前はもちろん「水沢第二洞門」
洞門の中にはお地蔵さんが。
昭和四十四年。
あれ、こっちは四十五年になってるぞ?
東側へ。
上を見るとスズメバチの巣がある。ここは海抜1300メートル以上。こんな所にもスズメバチっているんだなぁ。
西側より。
もう一枚、少し離れて。
先を急ぐ。
地理 ブログランキングへ
にほんブログ村
水沢エレナ写真集 『リアル』
(仮称)杉ノ谷第三隧道
【名称】不明
【所在地】勝浦市部原
【竣工】不明
【延長】約50m(地図読み)
【幅員】
【高さ】
2013年8月18日訪問
御宿町七本、現在地はココ(←クリック)で南の方向を向いている。
目的地は右のダート道の方にあるはず。
実はこのとき、別の隧道を目指しているものと勘違いしていた。
この先、本線は左の道。正面の登り道の先には以前は養鶏場があったようだが、現在では建物も撤去されたようだ。
現在地はココ(←クリック)で南の方向を向いている。
隧道は左の道の先。
轍の跡もなくなった。ここまできて、いい加減にちょっとおかしいな、と思い始めた。というのも、目指している隧道は車道にあるもののはずだったから。ちなみに、あとで確認したらその隧道はココ(←クリック)だった(^-^;
おかしいと思いながらも、地図の先には隧道の記号があるので、とりあえず前進を続ける。
とうとう杉林に。
そして、道は行き止まりに ∑(゚д゚;)
ここでようやく思い出した。
まきき氏のトンネルコレクションで見たアレだ!素掘り隧道2連発(地図には3本あるように描かれているが)の北側の方の隧道じゃないか。以前はなんとか通行可能だったのだが、2009年から10年の間に崩れて完全に閉塞してしまったようだ。
日暮れが近いので、軽く車道の隧道を取材して戻るつもりだったのに、とんでもない所にきちゃったぞ(^-^;
※ ※ ※
崩落した坑口の右をウロウロしたら、旧道と思われる道の切通しがあった。
(この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)により作成したものです。)
左が1894~1915年、右が1988~2008年の地形図。古くからある道だったことがわかる。
切通を過ぎての振り返り。右の斜面の下に隧道の南側坑口があるはずだが、木に邪魔されて全く見えず。日暮れも近いので、ここで引き返した。
ちなみに、こんなボツネタのような物件を登場させているのは、明日の記事への下準備みたいなものだったりする… ( ̄ー ̄)ニヤリ
※ ※ ※
先日、たまたま1枚目写真の所を車で通りかかったのだがビックリ。ちょうど2枚目の写真の辺りだろうか、土砂崩れで道が埋まっているではないか∑(゚д゚;) ちゃんと復旧されるのかな?
■参考サイト
トンネルコレクション:《勝浦市部原の廃隧道》 【1:古い地図帳は正しかった!】
古道・廃道 ブログランキングへ
にほんブログ村
杉谷昭子 演奏活動40周年記念CD シューベルト:鱒
(仮称)七本隧道
【所在地】勝浦市部原/夷隅郡御宿町七本
【竣工】不明
【延長】約20m(目測)
【幅員】約2m(目測)
【高さ】約2m(目測)
2014年12月15日訪問

昨日の記事から4ヶ月後、再び七本へ。今度はまきき氏と一緒だ。昨日の(仮称)杉ノ谷第三隧道へ至る道。昨年秋に続けてやってきた台風の影響か、大きな杉の倒木で道は塞がれていた。

隧道は前回と変わらぬ様子。もちろん本日のお題はこちらの隧道ではない。

(仮称)杉ノ谷第三隧道の閉塞地点から来た道を見下ろす。
そして今回のお目当てはこの左斜め先の道を行ったところにある。

まきき氏の言うままに山の斜面にある森林作業道のような所を進む。
この道はYahoo!やGoogleの地図には記載されていない。この先の写真を見てもらえば解るが、すでに道としての役割は終えている。

(この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)により作成したものです。)
冒頭のYahoo!の地図では解りにくいと思うので、今昔マップから作成した地図を掲載する。
左が1972年~1982年の地形図。右が現在の国土地理院の地形図だ。後者の赤丸部分に小さく隧道の記号が記されている。

100メートルも進むか進まないかのうちにこんな高さまで登ってきた。

隧道までは1キロもないはずなのだが、難儀しそうだ。

この辺りなど、それと知らされなければ道には見えない(^-^;

やがて掘り割り状の地形が現れた。おそらく路盤跡なのだろうが、雑草が群生し、その上に杉の倒木が折り重なるようにして倒れている。とてもじゃないが、前進できないので、たまりかねて、この先は路盤から離れて左手の小高い部分を進んだ。そちらでも半ば藪こぎが大変で写真は撮り忘れてしまった(^-^;

ずいぶん長いこと藪と格闘したような気がしていたのだが、写真のタイムスタンプを見ると10分程のことだったらしい。やがて道の状態は劇的に改善した。のだの人氏の言うところのツン区間からデレ区間への切り替わり。助かったぁ。この先、時折倒木はあったものの、隧道まで概ね道の状態は良好だった。

ここなど、このままでも遊歩道になりそうな素敵な状態(前後が大変なことになっているがw)

そして、(仮称)杉ノ谷第三隧道を後にして約30分後、いよいよ目的地へのカウントダウンが始まった(パノラマ合成)

隧道登場!
ところがここで、軽い恐怖体験。前方からイノシシの鳴き声が聞こえてきたのだ( ;・∀・)ハッ
思わず足がすくんだ。振り返るとご機嫌なまきき氏が。そうだ、いざとなったら、まきき氏を生け贄としてイノシシに差し出して逃げよう( ̄ー ̄)ニヤリ ということで、方針も決定して隧道に。
※ちなみにイノシシの声は谷の向こうから発せられているようだった。

南側坑口。
縦横各2メートルといったところだろうか。
よかった、閉塞してなさそうだ。このまま元来た道を帰りたくなかったので、ホッとした。気がついたら日暮れまであまり時間がなかったので、かなり心配になっていたのだ。

南側坑口から内部を望む。
内部は細かい崩落が進んでいるようだ。

内部から見た南側坑口。

隧道の中央部分の崩落。
ちょっと頭が涼しくなってきた(^-^;

北側の坑口は埋まりかかっている。今のところはなんとか通り抜け可能だが、いつまで大丈夫かなぁ。この写真はもう1年前なので、ひょっとしたらもう・・・(汗)

坑口を這い出る。

続いてまきき氏も。

南側坑口(パノラマ合成)

北側で再び道は荒れ出した。

廃隧道の手前って、倒木がバッテンになっていることが多いなぁ。

そして再び倒木が積み重なるツン区間に。向こう側から来たらどこが道なのか解らなくなってたかもしれない。

ツン区間は50~100メートルぐらいか。また作業道レベルだが綺麗な道が復活。

やがて東京電力の保守用の標識が現れた。ここまで来ればもう安心。

この付近の杉林は七本優良森林団地というらしい。しかし、倒れた杉を見ると林業の問題点が見えてくるようでちょっと考えさせられる。

やがて広場に出た。ここまで車が入ってくるのだろう。こっちから行けば近かったなぁ。まきき氏にハメられた(^-^;

振り返り。
ここが山道への入り口。

出発点の近くにチャリの所まで歩いて戻る。
教訓。今度はもう少し時間に余裕を持っていこう(^-^;

古道・廃道 ブログランキングへ

にほんブログ村


石田流の基本―本組みと7七角型 (最強将棋21)

古都辺取水場
【所在地】市原市古都辺
2014年9月21日訪問

市原市古都辺(こつべ)。現在地はココ(←クリック)、進行方向は北。
右手に水道施設らしき建物が見える。ちょっと寄り道していこう。」

上の写真から少し下ったところ。巨大な水管が登場。

接合井ってなんだろ?と思ったら、「濾過池と配水池をつなぐために、その間に作られた井戸」(「コトバンク」より)とのこと。航空写真を見ると、確かに水管の上に貯水池のようなものが写っている。

さて、下に降りてきた。

「古都辺取水場」

さらに裏に回り込んでみた。現在地はココ(←クリック)
ん、ガードレール!?Σ(゚д゚)

どうしてあんなところにガードレールがあるんだ??
地図を見ると、手前の小川(支川村田川。これでも一応二級河川)を渡った道が描かれているが、道の存在は気づかなかった。航空写真を見ても道は残ってなさそう。もしかしたら、長柄ダムができる前に使われていた道の跡なのかも。

長柄方面への暗渠。ここで道は行き止まり。

さて、引き返して、北に向かう。

ここで舗装路は支川村田川の右岸に移る。

橋は残念ながら無名橋。西側より。

橋の上から南の上流方面を望む。
この先に関東最大のアースダムあるようには見えないのだが、長柄ダムの水源は実は利根川。房総導水路を通じて栗山川の横芝揚水機場からはほぼ地下を通じてダムまで水が引かれている。

北の下流方面。

あれっ、野良ニワトリ(^-^;
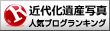
近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村


コッペパンはきつねいろ (偕成社文庫2001)

PR: 新しい介護食品“スマイルケア食”とは-政府ネットTV
浜川2号橋
【名称】浜川2号橋
【所在地】山武郡九十九里町小関
【竣工】1998(H10)年3月
【延長】約4m(目測)
【幅員】約8m(目測)
2014年8月3日訪問
片貝海岸近くの住宅地。
通りに出た。
作田川の支流・浜川に架かる橋。南側より。
西側より。
橋長は幅員の半分ぐらいしかない(^-^;
南側左の銘板。「浜川2号橋」
南側右の銘板。「浜川2号橋」
橋の上から西の上流方面を望む。
東の下流方面。
ここが2号橋ならあれが1号橋かな?
北側より。
北側右の銘板。「浜川2号橋」
北側左の銘板。「浜川2号橋」
この短い延長なのに律儀に4枚の銘板。しかも全部同じ内容だし(^-^;
東側より。おやっ、もう一枚銘板があるぞ。
「平成10年3月」
おかげで建設時期が判明。
今度は左岸の東側より。
橋のすぐ下流で川の幅員が一気に倍になる。さて、次の橋(1号橋?)に向かおう。
※ ※ ※
【名称】不明(浜川1号橋?)
【所在地】山武郡九十九里町小関
【竣工】不明
【橋長】約8m(目測)
【幅員】約3m(目測)
2014年8月3日訪問
西側より。
北側より。
あらら、残念ながら銘板の類がなくて、橋名は不明。状況的には浜川1号橋でほぼ間違いないのだとは思うのだが…
橋の上から西の上流方面を望む。先ほどの浜川2号橋が見える。
東の下流方面。水門の先はすぐに作田川との合流点だ。
地理 ブログランキングへ
にほんブログ村
Premium 浜川瑠奈 [完全版]
梅田隧道
【名称】梅田隧道(うめだずいどう)
【所在地】横須賀市浦郷町/船越町
【竣工】(M20)年3月(現地案内碑より)
【延長】204m(「平成16年度道路施設現況調査」より)
【幅員】5.0m(同上)
【高さ】3.7m(同上)
2014年10月19日訪問
横須賀市浦郷町の住宅地。現在地はココ(←クリック) 進行方向は西。
記念碑があった。
「梅田隧道碑」
写真を見れば解るが、横須賀市内で軍用を除いた最古の隧道とのこと。こりゃ期待できそうだ!(・∀・)ニヤニヤ
ギャー全部漢文だよ( ;´Д`) 交通が大変だからがんばって隧道造りました的な事が書いてあるようだけど、とてもじゃないけど、全文読み通す事ができないオイラ(^-^; なお、この文字を記したのは海軍大将正二位勲一等功二級伯爵・樺山資紀(Wikipediaによれば、位階は最終的には従一位)。明治の海軍軍人で、海軍大臣、内務大臣、文部大臣、警視総監、初代台湾総督、枢密顧問官などを歴任した超大物。
こういうものを見るたびに思うのだが、昔のエライ人は本業以外にも素養があったということ。軍人といえば筋肉バカ的なイメージで、乱暴な発言と駄洒落で人気者になった自衛隊の元幕僚長などがいたりするが、まぁ、ゴニョゴニョ…
ところで、後日、2013年10月放送のタモリ倶楽部の動画(アノ人が案内人)を見返したところ、タモさんは「絶対あれ読まないと気が済まないから」と言ってた(^-^;
石碑の前には、無教養なオイラでも容易に解る案内板が。ありがたや(^-^;
ところで、この案内板、旧仮名遣いでありながら、漢字はなぜか新漢字だぞ(^-^;
さて、案内板のおかげで、期待度アップ。行くで、坂道君!
坂道を登り切ったところ。右手のゴミ捨て場にパソコンが捨ててあった。まきき氏を呼べば喜んで拾いに来そうだったが、ここまでの道を説明するのが面倒でやめておいた(^-^;
いよいよ隧道の登場!
だが… ええっ、あれが明治中期に竣工した古隧道?? ∑(゚д゚; )ガーン
と、と、とりあえず、落ち着いて、補強された法面を…
さて、一息ついて隧道に。北側坑口。
ちょうどここで、まきき氏から電話が入った。「えへへ~、もしかして、●●●に車停めてますぅ?」 そう、この後、某スペシャリスト集団の方々とのマル秘探索が控えていたのだ。しかし、せっかくの横須賀遠征だというのに、チャリを持ってこなかったまきき氏!ごめんよ、プレ探索はおいらだけ楽しませてもらっちゃって(^-^;
隧道内部はコルゲート補強されている。なんだか、房総の林道の隧道みたい。ちょっと親しみを感じる(^-^;
そうそう、タモリ倶楽部で「なんか出そう」と言ってたのがいたぞ。カニング竹山?それとも江川達也? なんだよ、そのクソな感想はヽ(# `Д´)ノムキー!!
↑隧道を見て「出そう」という感想を聞くと、とにかくイラッとしてしまうオイラ(^-^;
北側の扁額。「梅田隧道」
北側坑口から内部を望む。
内部から見た北側坑口。
隧道の延長は約200メートル。住宅地にある隧道だから、照明や補強ぶりは万全。
そしてみたびダモリ倶楽部ネタ。
タモさん、「横須賀の人っつのは気が短いんですね、(一同爆笑) 絶対迂回はイヤなんですよ」
と・・・ なかなか鋭い指摘!
しかーーーし、ソレを言ったら、房総の人は横須賀の人の数百倍気が短いゾ!!!と断固言いたいオイラだ。
※このサイトにいらっしゃる方には今更実例を挙げる必要はないだろう・・・w
まきき氏!いつの日か、房総人の短気ぶりを全国にアピールしてくれ!!!ww
チャリを漕いで何の問題もなくあっという間に南側坑口へ(問題があったら大問題)
南側の扁額。「梅田隧道」
南側坑口から内部を望む。
内部から見た南側坑口。
南側より。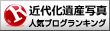
近代化遺産 ブログランキングへ
にほんブログ村
梅田本―「梅田の寄り道」が何十倍も楽しみになる300軒!! (えるまがMOOK)
樽沢橋
【名称】樽沢橋(たるさわはし)
【所在地】南アルプス市芦安芦倉
【竣工】不明(1962年頃?)
【橋長】約20m(目測)
【幅員】約4m(目測)
2014年10月26日訪問
山梨県道37号、南アルプス公園線。
ガードレールに腰掛けて一休みしていると、正面の落石防護ネットの扉が気になった。
よく見ると鍵かかっていないし…
おそるおそる扉を開いて、階段に足を掛けてみた。
登れるところまで登ってみた。これ以上は、まぁ無理することもないだろう(^-^;
再び県道を歩き出す。
トレッキングシューズを履いた足が痛くなってきた。まずいよ、あと15キロもあるってのに( ;´Д`) 舗装路なので普通のスニーカーにするべきだったよ( ;´Д`)
橋が見えてきた。県道起点側から5本目の橋。隧道のことばかり考えて、ここに来たのだが、成り行きで橋も全部撮影することに。とんでもない手間になってしまった(^-^;
北側より。
今度の橋は樽沢橋。ネットの地図ではタル沢と記載されている。
北側左の親柱。「樽沢橋」
北側右の親柱。「たるさわはし」
袂の大岩になぜか金属製の梯子が設置されていた。コイツもおいでおいでしているぞ。
せっかくなので梯子の上からのアングルもゲット(^-^;
車でもやってくれば面白いのに… しかしここはマイカー規制区間。ここまで、県道上で見かけた車両は奈良田に戻るバスだけ(この後、乗り合いタクシーなども見かけたが)
橋の上から東の野呂川方面を望む(パノラマ合成)
西の沢側。パノラマ合成したら、妙にこぢんまりしてしまった(^-^;
なので、大きな一枚も。
あ、広河原行き2往復目のバスだ。なんだ、梯子降りちゃったってのに。。。
南側より。
南側左の親柱。「樽沢橋」
南側右の親柱。「たるさわはし」
横からの姿も撮りたいところだが、これが精一杯(^-^;
よし、次に行こう。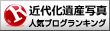
近代化遺産 ブログランキングへ
にほんブログ村
【吉野杉の木香がのった本格的な本生樽酒です】一品 樽生酒本醸造酒 720ml
高宕線の水路隧道
【所在地】君津市怒田沢
【竣工】不明
【延長】約15m(目測)
【幅員】約3m(目測)
【高さ】約3m(目測)
2014年3月9日訪問

君津市怒田沢の林道高宕線にて。場所はたぶんこの辺り(←クリック)か?西日笠方面に進んでいる。

落石注意の標識。そしてその先は…

ホントに崩れてるw
たぶん2月に降った雪の影響で崩落したのだろう。

少し進むと砂防ダムが現れた。

銘板。

あの穴は何だろう?

沢の水はこの暗渠で川に流れ出す仕組み。
※ ※ ※

しばらく進むとコンクリ舗装らしきものが見えてきた。「やった、これで楽できる」と思ったら…

暗渠の上がコンクリになっているだけだった。この右になにかありそうだ…

1枚上の写真、右の法面に埋め込まれているプレート。

右に進むと何か見えてきた。

またもや砂防ダムの登場。こちらの沢は道のように広くなっている。この先、どうなっているのかちょっと気になるが、時間も気になるのでそれは次回に。

銘板。
※ ※ ※

林道の本線に戻る。

川を見下ろす。

またもや落石注意の標識が。
そうそう、そういえば、某M氏だが、ある日の夕方に何も考えずにこの林道に車で入り込んだそうだ。しかも、そのまま通過してしまったとか。
この日、そんな事をしたら、間違いなくオワタな事になっていたなぁ(^-^;

すぐ先には反対向きに普通の落石注意の標識もあった。
※ ※ ※

やがて築堤が現れた。ここから川は道の左から右に移動する。ということは当然…

左を見ると川が隧道に吸い込まれていくのが見えた。

川床に降りられる踏跡があったので、行ってみることに。

立派な水路隧道があった。
隧道の右が築堤で、写真右が来た方向になる。

築堤部分が本来の川の流れなのだろうか?

こりゃ、すごいぞ。

西側坑口。

中まで行けそうだ。

足を滑らせないように慎重に…

水は手前から正面方向に流れている。

見上げると目に飛び込んでくる景色。

う~ん、水の中を歩かないと通り抜けは無理そう。

ここが靴で行ける限界地点。水路隧道なので洞床は複雑に削られてそう。長靴でもうかつに足を踏み入れると水没するかも(^-^;

内部から見た西側坑口。

東側からの姿も拝みたいところだったのだが、西側と違って川床への明瞭な踏跡がなく、降りてみても戻れなくなってしまったら大変なので止めておいた。なにしろ独りだから。最悪、ずぶ濡れになって隧道を通って西側に抜ければ戻ることができるのだが、3月初めのまだ寒い時期だったので。人気のない山の中で独りなのに無茶なことはできないよなぁ(^-^;
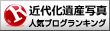
近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村


1/700 艦隊これくしょんプラモデルNo.02 艦娘 重巡洋艦 愛宕

女ヶ倉橋
【所在地】市原市大久保
【竣工】1985(S60)年3月
【延長】約50m(目測)
【幅員】約4m(目測)
2014年10月12日訪問

市原市大久保にある林道女ヶ倉線の起点(終点?) 現在地はココ(←クリック) 正面は10時の方向。ここまで来る途中、「女ヶ倉線通行止」の看板を何度か見かけたが、とりあえず行けるところまで行ってみよう。

道から見下ろす光景はなかなかの見もの。

路肩が少しだけ決壊している。ここから飛び出したら大変なことになるなぁ。

道はますます高度を上げ、おいらはちょっと疲れてきた(^-^; ん、いよいよか?

「全面通行止」とは書いてあるが、どうなっているのかな?もうちょっと行ってみよう(^-^;

鉄パイプのバリケードの先も道は特に問題なし。ただ、車が通らなくなって若干ゴミというか枯れ葉や枯れ枝の類が目立つ程度か。

橋が見えてきた。手前右手の法面にブルーシートが掛けられている。

これぐらいで通行止めにすることもないのに… 紅葉シーズンに向けての念のための措置か?なんて思っていたら…

あれま、こりゃたしかにマズいわ。橋台の裏側の土砂がゴソッと流れ出してるよ(^-^;

東側左の銘板。「めがくらばし」

東側右の銘板。「昭和60年3月竣工」

橋の上から北側を望む。
山と木しか見えないが、なぜか遠くから盆踊りの音楽が聞こえてきた。養老渓谷あたりで何かイベントでもやっていたのだろうか?(^-^;

南側は木がワッサワッサ。

西側より。

西側左の銘板。「女ヶ倉橋」

西側右の銘板。「昭和60年3月竣工」
※ ※ ※

橋を過ぎて少し進むと分岐が。現在地はココ(←クリック) 右の道の先に先ほどの女ヶ倉橋があるので、来た道を振り返る形になる。

ここから先は林道牛堀線。このまままっすぐ進めば折津の奇岩の正面に出るはず。

やがて通行止め区間は終了。
場所はココ(←クリック) やはりこれも来た方向に振り返っての写真となる。

バリケードの先は、またもや別の林道との分岐。

その先は林道月崎大久保線で、ひたすら直進すれば小湊鐵道の月崎駅近くに出るようだ。
おいらはそのまま女ヶ倉線を西に。

そのまま大福山の展望台の下を通り女ヶ倉線の完抜完了。、

このまま石塚集落方面へ。

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村


若潮酒造 千亀女 芋25度1800ml





























