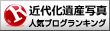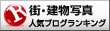【所在地】君津市広岡
【竣工】不明
【延長】約50m(目測)
【幅員】約4m(目測)
【高さ】約5m(目測)
2014年4月13日訪問

君津市広岡。現在地はココ(←クリック) 地図に記されているニョロッと少しだけ伸びている道を正面に見ている。

ここは、今昔マップを見ていて気がついた。YahooやGoogleの地図では50メートルで道は終了しているが、少し前の地図やマピオン、国土地理院の地図などでは西にある山の北側をぐるっと回り込んで上総松丘駅近くで国道411号につながる線形が描かれている。

入り口から200メートルほど進んだ地点。3つの赤丸の場所に穴があった。真ん中は築堤の下を通る水路だが、左右のものはちょっと寄り道してみたくなる物件。

まず、左の小さめの水路隧道を。上に乗ったら崩れちゃいそう(^-^;

反対側より。

次は右の水路隧道を。こちらは結構立派。

反対側から。

水路隧道を過ぎると、道はだんだん不明瞭になってくる。

いつの間にか左の水路はどこかに消えてしまった。周囲は再び杉の植林地に。

右の水の流れもなくなった。川の底なのか道なのか解らない凹みを進む。

周囲はみたび植林地に。
実はこの数週間前にもここまで来たのだが、日が暮れて鹿らしき生き物が走るのが見えたので、引き返したのだった。

東電の鉄塔の案内標識かな。

そうそう、前回もこれを見て途方に暮れたのだ。どうやらこの先はゴルフ場の地所らしい。

しかし、今回は時間もたっぷりあるし、下調べもしてきた。道はこの辺りで左にカーブしているはずなのだ。
実は、のだの人さんの動画をチェックしたらここがあったのに気づいたのだった(^-^; ま、まぁ、あの方向が怪しいとはお、お、思ったんだけどね… 時間がなかったから行かなかったのだけど・・・

おっ、おそらしい雰囲気になってきたぞ!

堀割の先は右にカーブしている。

隧道登場!

東側坑口。

思いがけず、断面の大きな隧道。

東側坑口から内部を望む。

内部から見た東側坑口。

内部は一応側溝も完備。しかし道の中央にも溝があったりする。

ここの地層は独特。

延長は50メートルぐらいだろうか。

西側の道は状態良好のようだ。

いつの間にかU字溝が現れた。泥で埋まっているけど(^-^;

内部から見た西側坑口。

隧道を抜けたところで振り返り。

西側坑口。

うむむ、、通り抜けてきちゃったよ(^-^;

西側の道は刈り払いもされている。

少し下ると舗装路が現れた。こっちから行った方が断然楽だったよ(^-^;

この上には城跡があるようだ。隧道の仮称はここからとらせてもらった(広岡隧道は別にあるので)

ひとつ上の写真の穴。
※ ※ ※
おまけ動画
東側より
西側より

古道・廃道 ブログランキングへ

にほんブログ村


1日1分レッスン!新TOEIC Test 千本ノック! 祥伝社黄金文庫